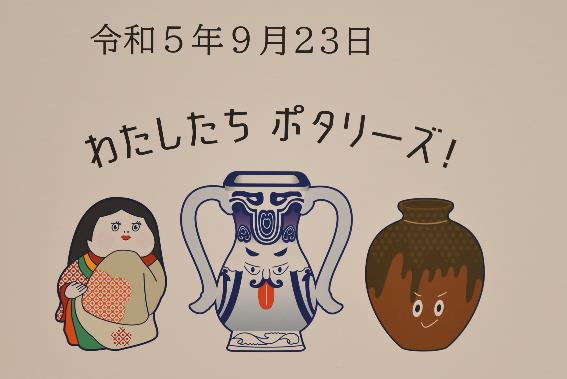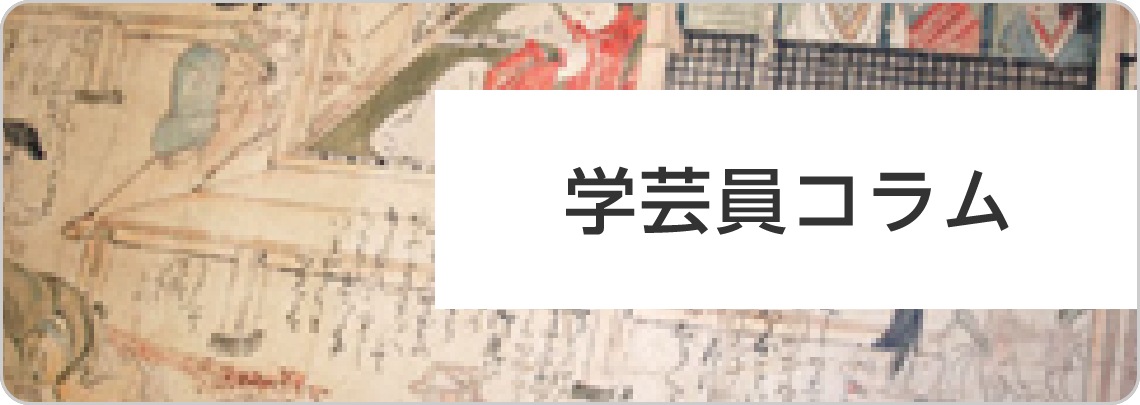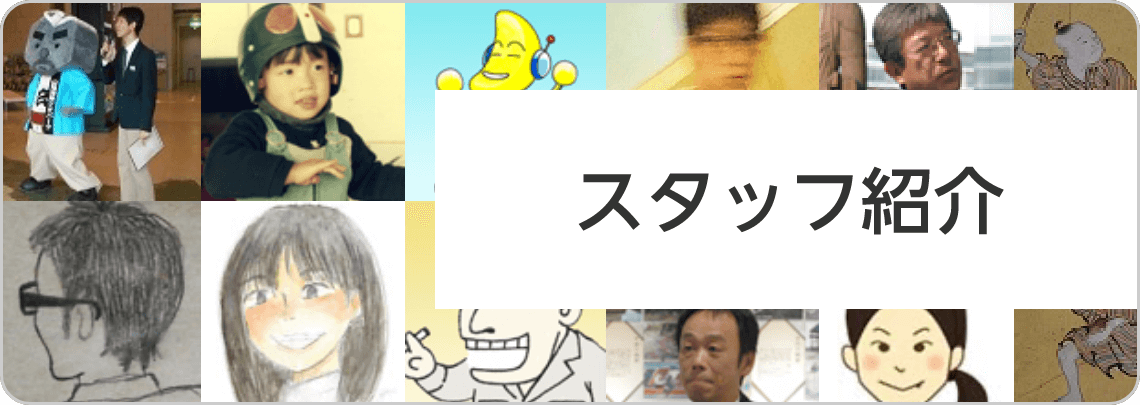学芸員コラム
2025年5月21日
第166回 姫路と産業遺産
はじめに
もともと兵庫県教育委員会で埋蔵文化財調査の専門職員であった私は、JR姫路駅の高架化工事に先立ち、工事予定地での埋蔵文化財の有無を確認する発掘調査を平成18年度(2006)に担当し、そこで明治21年(1888)に姫路駅が開業した際に建設された機関車転車台(ターンテーブル)のごく一部を発見したのです。その後の本格的な発掘調査は同僚が担当することになり、その結果、煉瓦で築かれた転車台の全体像が明らかになりました。この調査が、私が産業遺産と向き合うきっかけとなったのです。

1 産業遺産について
産業遺産が最初に注目されるようになったのは20世紀の英国のこと。第2次世界大戦が終わった後に産業革命時に使われた機械や装置の廃棄が進み、これに対してかつての労働者を中心に保存運動が活発化したのです。現在、産業遺産の定義に時代の限定はなく、「歴史的、技術的、社会的、建築的または科学的に価値のある産業文化の遺物」で構成されると定められています。
わが国の産業遺産には、普段何気なく利用している駅舎や橋梁、公共施設、町工場等、生活に身近なものが多く、それゆえ実態や価値が十分に把握されないまま、取り壊しや改変が進められる事例が少なくありません。近年は国や自治体を中心に「近代化遺産」という枠組みで調査が進められ、その文化的な価値が認められて文化財となる例も出てきました。また、それらの中には地域活性化の拠り所として期待・活用される事例も見られます。
2 姫路・播磨地域における産業遺産の事例
姫路は近代以降、工業都市として発展を遂げてきました。そのため市の周辺には数多くの産業遺産が所在します。ここではその一例を紹介いたします。
(1)煉瓦造工場建築
旧大同燐寸姫路工場(建築年不明/現存せず)

日本における煉瓦建築の出現は幕末の長崎のこと。その後、明治期に煉瓦は建築や土木構造物の建設資材として急速に普及しますが、明治後期には鉄筋コンクリートの技術の普及と入れ替わるように減少し、大正12年(1923)に発生した関東大震災を機に、その使用量は激減していきます。
山陽新幹線高架橋の北側、船場川右岸にかつて存在した煉瓦造の工場建築です。もとは東洋燐寸(マッチ)姫路工場の建物で、同社は神戸で大正6年に設立されました。昭和2年(1927)に外国企業であるスウェーデンマッチ社が出資して大同燐寸が設立され、その後は同社の姫路工場として稼働しました。この工場は日本毛織などの繊維工場とともに大正期の「旧姫路市域内の八大工場」の一つに数えられましたが、現在これら八大工場はいずれも現存していません。戦後、船場川の対岸に姫路モノレールの軌道が建設され、近現代の二つの特徴的な構造物が対峙するという独特の景観を形成していました。
(2)鉄道敷設に関する産業遺産
このコラムの冒頭で、姫路駅での機関車転車台(ターンテーブル)の発掘について触れました。この転車台を設置した山陽鉄道会社は明治21年1月に設立され同年12月には兵庫-姫路間が開通しました。明治34年には神戸-下関間が全線開通し、この路線はいまのJR山陽本線のもとになりました。同鉄道が建設したとみられる、橋脚や橋台など煉瓦造の構造物は山陽本線の路線に残っています。これらの分布調査を行った結果、建設年代の差によって煉瓦の色や大きさ、積み方などに明確な型式差が存在することが明らかになりました。


また、JR播但線の前身である播但鉄道に関しても、橋梁の橋脚や橋台に路線敷設時に設置された煉瓦造の構造物が残されています。これらは近代以降急速に鉄道路線網が姫路や兵庫県内にも広まっていったことを示す証拠と言っても良いでしょう。
(3)高度経済成長期に関する産業遺産
①姫路モノレール

姫路駅前と手柄山中央公園との区間で姫路市交通局が運行したモノレールで、昭和41年5月に開業し、昭和49年4月まで運行されました。終点の手柄山は姫路大博覧会(昭和41年4月3日~6月5日)の主会場となっており、開通当初は会場への旅客輸送の役割を担いました。

姫路モノレールはわが国では2例しかないロッキード式モノレールで、その技術的な特徴は駆動輪がゴムタイヤではなく鉄車輪であり、橋桁の上面と側面に設置された支持レールにより走行することです。航空機製造技術を応用して生まれた全アルミニウム合金製の車両は、かつての手柄山駅跡(現手柄山交流ステーション)に保存され、さらに高架橋の橋脚跡が姫路駅西エリアなどに現存しています。時折、廃線跡を巡るウォーキングイベントが開催される際には数多くの参加者が集まるなど、現在も多くの人々の関心を集めています。
②波賀森林鉄道

播磨地域の西端部、宍粟市波賀町は豊富な森林資源に恵まれ、大正から昭和にかけて、国有林からの木材輸送のために森林鉄道が活用されました。大正13年に約24.6kmの幹線が完成し、以降、次々と谷筋ごとに支線が延びていきました。戦後復興期から高度経済成長期にかけてわが国の木材供給に寄与しましたが、徐々に木材輸送手段がトラックに移行し、昭和43年(1968)7月15日の「閉鉄式」を最後に廃止されました。

宍粟市波賀町の地域活性化を目指して結成された波賀元気づくりネットワーク協議会により、森林鉄道廃止からおよそ半世紀後の平成30年から廃線跡の現地調査を行うとともに、幹線開通から1世紀後の令和6年(2024)10月には全長678mの軌道を新たに敷設して機関車を運行するなど、波賀森林鉄道の「復活」を果たしました。この復活は、波賀町の産業の歴史を学ぶ生きた教材となるともに、波賀町の賑わいを取り戻す活動の原動力として期待されます。
3 まとめ
広い意味での産業は、生活をいとなむためのさまざまな生業を指し、その数だけ無数の産業遺産が存在するともいえますが、実際に保存が実現するものは決して多いとは言えません。
特に最後に紹介した波賀森林鉄道では、地域に住む人がこれを地域の誇りとなるものと認め、管理者の理解を得て、その調査、及び普及啓発に努め、産業遺産の保存を実現させています。調査から保存、活用に至る好循環となっており、産業遺産保存のお手本のような存在といえるかもしれません。