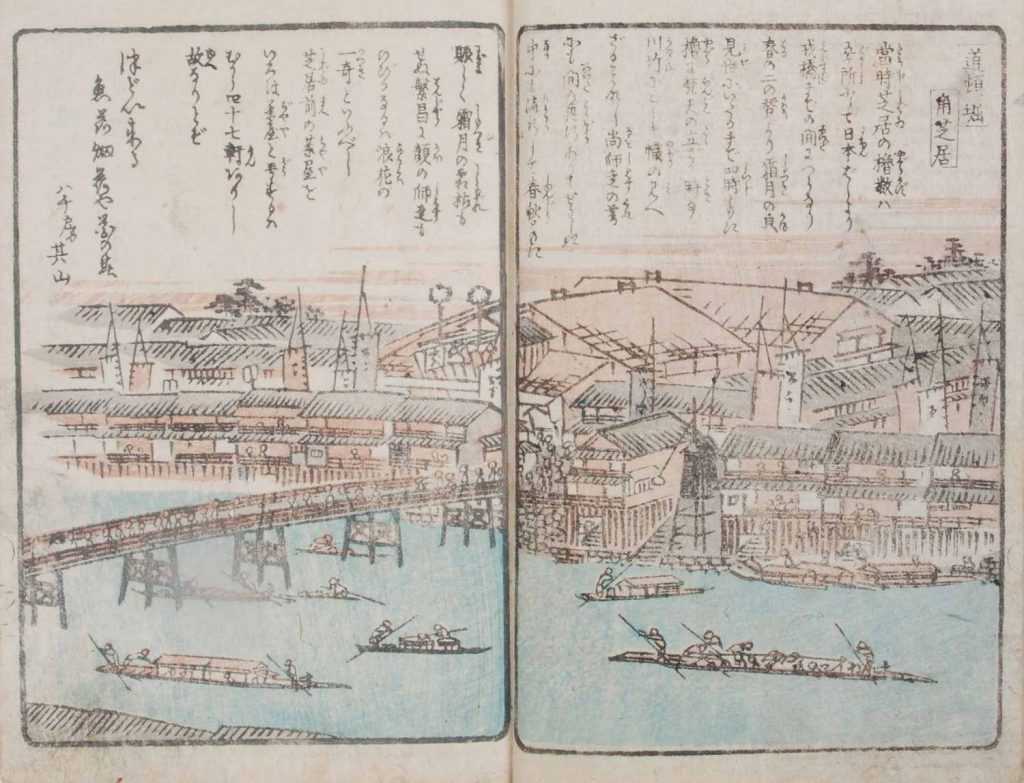洲本八狸
淡路島(あわじしま)の洲本(すもと)の町を見守るように、背後にそびえる三熊山(みくまやま)。この山に住むという狸が芝右衛門狸(しばえもんだぬき)である。芝右衛門狸は、佐渡島(さどがしま=現在の新潟県佐渡市)の団三郎狸(だんざぶろうだぬき)、讃岐国屋島(さぬきのくにやしま=現在の香川県高松市)の禿狸(はげだぬき)とならんで、日本三名狸にあげられる有名な狸だ。なお、「芝右衛門狸」は「柴右衛門狸」とも表記されるが、ここでは古い文献の表記を尊重して、「芝右衛門狸」で統一したい。
三熊山の山頂部には、中世の安宅(あたぎ、「あたか」とも言う)氏の城に由来するとされる洲本城がある。現在は、江戸時代はじめに脇坂安治(わきざかやすはる)が築いた石垣が残る。大坂夏の陣以降、淡路国は蜂須賀(はちすか)氏の阿波国(あわのくに=現在の徳島県)徳島藩領となり、寛永12(1635)年から重臣の稲田(いなだ)氏が城代として洲本に入る。しかし、稲田氏時代の洲本城は山麓部に築かれたもので、三熊山の山頂部は使われていなかった。現在は、1928(昭和3)年に昭和天皇即位式に合わせて建設された模擬天守閣が、町を見下ろしている。
主郭跡の片隅には、芝右衛門狸をまつる祠(ほこら)があり、中には狸像がまつられている。これは1962(昭和37)年に片岡仁左衛門(かたおかにざえもん)、藤山寛美(ふじやまかんび)といった、大阪の芸能人たちが寄進したものである。今は解体された道頓堀中座(どうとんぼりなかざ)にも、「おたぬきさん」と呼ばれる芝右衛門狸をまつる祠があった。大阪の芸能人たちにも、芝右衛門狸の話は親しまれていたのである。
近年、洲本ではこの狸伝説を生かした町おこしに取り組んでいる。きっかけは1999(平成11)年の大阪中座の閉館で、そこにまつられていた芝右衛門狸が洲本に帰ってくる話がもちあがったことにあった。今では芝右衛門狸をはじめとする8つの狸の石像が街の各所に建てられ、八狸(やだぬき)マップも作られて、狸を訪ねながら街を散策できる。8つの狸の話は、『洲本八だぬきものがたり』(2002年、アリス館)として刊行されているので、これにもとづいてそれぞれ紹介していこう。
まず、芝右衛門狸は、洲本八幡神社の境内にいる。石像の背後には、大阪中座から洲本に帰ってきた芝右衛門狸をまつる社殿もある。社殿の前にある舞台には、「大阪中座 お狸さん」という額がかけられている。神社のお話では、大阪中座から芝右衛門狸が帰ってきたときに、もとからあった舞台の後ろに、新しく社殿を建設したものという。

芝右衛門狸の息子が「いたずらだぬきの柴助(しばすけ)」で、洲本八幡神社の門前の足湯の脇にある池の中に立っている。子供のころは芝右衛門に教えてもらった化ける術で街の人にいたずらばかりしていたが、あるとき思い立って北前船(きたまえぶね)に乗り込んで蝦夷地(えぞち=現在の北海道)まで大冒険に行ってからはしっかりしてきたそうだ。途中の越後国柏崎(えちごのくにかしわざき=現在の新潟県柏崎市)の港で見た花火大会が忘れられず、洲本へ帰ってからは仲間を集めて花火に化けては町の人を楽しませたという。
八幡神社から西へ、厳島神社の境内にいるのが「夜まわりだぬきの武左衛門(ぶざえもん)」である。町の武家屋敷の人たちが戸締まり、火の用心をしないことを見かねて、毎晩役人に化けて見回りをしていたという。

さらに商店街のアーケードの中には「買いものだぬきのお増(おます)」がいる。お増狸は芝右衛門狸の妻で、芝居見物にうつつをぬかす芝右衛門狸の留守をまもって子育てをした、しっかりものの狸だ。お増狸は街に出て買い物をするのを楽しみにしていたが、払うお金はやはり晩になると木の葉になってしまうものだった。でも、なぜかお増狸が来た店はそのあと商売繁盛するようになるので、街の人たちにはとても人気があったという。

アーケードの西の端、千草川(ちくさがわ)の橋のたもと近くには「河守りたぬきの川太郎(がたろう)」がいる。一家みんなが川太郎という名前で、人間の姿に化けては川の掃除をしたり土手を直したり、あるいは川で仕事をする街の人たちを助けたりする狸とされている。

川太郎狸がいるところから、寺町筋(てらまちすじ)を北へ行き、城下町の西北の出口にあたる洲本川沿いにたたずむのが「頼母子講(たのもしこう)だぬきの宅左衛門(たくざえもん)」である。洲本狸の長老で、たくさんの蓄えを持っていて、困った狸があると分け与えて助けてあげたという。また、みんなで少しずつ蓄えを出し合って、くじで当たった人に順番に融通しあう頼母子講というしくみをはじめた狸ともされている。

洲本川沿いには、紡績工場(ぼうせきこうじょう)の煉瓦建築(れんがけんちく)を活用した、商業施設や市立図書館がある。ここに、「美人だぬきのお松」がいる。芝右衛門狸の娘で、洲本で評判の器量よし、結婚を申し込む狸はたくさんいた。いったん阿那賀(あなが)の与茂太夫狸(よもだゆうだぬき)の熱心な求婚にほだされて嫁入りしたが、遊び人の与茂太夫狸はすぐに家をあけてしまうようになったので別れ、最後は台場の伊助狸(いすけだぬき)と結ばれて幸せに暮らした、という。

最後に、市役所近くの堀端筋(ほりばたすじ)の交差点の隅に「大入道(おおにゅうどう)だぬきの桝右衛門(ますえもん)」がいる。この像、何をかたどっているのか、一目ではよくわからない。なまけものの狸で、いつも昼間からお酒を飲んで寝てばっかりいたという。この像は、どうやら丸いおなかの上にお酒を飲むおちょこを乗せて寝転がっているところのようだ。ただし、桝右衛門狸はいつもごろごろしてばかりいたわけではない。小僧さんに化けて、夜になって帰り道に困っている老人の道案内をしたり、悪い男にいやがらせを受けている娘さんを大入道に化けて助けてあげたりした、という。

この芝右衛門狸の話、最近洲本の人々によってリライトされた絵本(『しばえもん』、2000年、淡國書房)もある。この絵本では、中座で芝右衛門狸が犬に殺されるという筋は避けられ、また洲本に戻って穏やかに暮らすように改変されている。洲本を訪れた日、編集にたずさわった書店主のお話をうかがうことができたが、執筆者の間で、子供向けの話なのにかわいそうすぎる、ということで、あえて平成の芝右衛門狸を書こうということで改変したのだそうだ。

伝説は時代によって少しずつ変わっていくが、このエピソードは今まさに変わろうとしている姿を示しているのだろう。ほかの伝説にもみられるように、昔話や伝説には、人が死んだり不幸になったりという悲しい話がよく出てくる。かつてはそのことに意味が見出されていたはずなのだが、今日の目から見ると、もっと楽しく幸せな話の方が受け入れやすいのだろう。
実際、芝右衛門狸の話は歴史の中で大きく変容してきたようだ。古くは、天保12(1841)年の『絵本百物語(えほんひゃくものがたり)』にすでに見える。ただし、そこでは洲本で芝居を見に行って犬に殺されたという話で、大坂まで出ていく話にはなっていない。中座の話は、大坂で独自に発展したものが、明治以降に洲本に持ち込まれたとも考えられている。
また、1922(大正11)年に公表された論文では、このサイトで紹介している芝右衛門狸と阿波の禿狸の化けくらべの話は、京都伏見で土地の狐と化けくらべをして、芝右衛門狸が大名行列を勘違いして殺された、という話で載せられている。狐と狸の化けくらべの話は佐渡の団三郎狸にも見られ、こちらの方が古い形と見てよい。なお、阿波の禿狸とは、日本三名狸にあげられている、隣の讃岐国屋島の禿狸のことと考えられる。どこかで両者が結び付けられるようになったのであろう。
さらに、柴助狸やお増狸など、芝右衛門狸以外の狸についても、幕末以降に語られはじめたと見られている。たしかに、紹介した8つの狸のキャラクターはいずれも親しみやすく、とても新しい印象を受ける。
いずれにせよ、洲本には狸にまつわる話が数多く伝えられてきた。これは四国の特徴と重なるもので、四国にも多くの狸伝説が残されている。淡路島は、現在は兵庫県に含まれているが、古代では四国や紀伊国(きいのくに=現在の和歌山県)と同じ南海道(なんかいどう)の一つとされたように、歴史的には四国や紀伊とのつながりが深かったのである。俗に「四国に狐なし」と言われ、四国では狐伝説はほとんどなく、その位置を狸の伝説が占めている。洲本の狸話には、こうした地域性がよく表れている。
用語解説
狐に化かされる

姫路に伝わる「およし狐」伝説。この話は人に助けられた狐が恩返しとして人の妻となる「狐女房」型の話と言えるが、一般的な狐女房の話は、狐が人の妻となるものの正体を見破られて去っていく、という話が多い。この伝説の「およし狐」は嫁入りを避けて、人間に幸せな結末をもたらしている。こうした筋立ては、一般的な狐女房話よりは新しい時期のものと考えてよいだろう。
ただし、「およし狐」の名前自体は中世末期の文献までさかのぼることができる。天正4(1576)年の奥書がある『播磨府中めぐり』で「梛寺(なぎでら)の小よし狐」と記されていて、少なくともこのころから、姫路で語られ続けてきたことがうかがえる。
寛延3(1750)年の『播州府中めぐり拾遺(しゅうい)』では、梛寺の柱が動くことがあり、これをおよし狐の仕業と伝えている。梛寺は、姫路城下町建設以前には姫山近くの梛本(なぎもと)というところにあった寺で、現在は市内の坂田町(さかたまち)にある善導寺(ぜんどうじ)の前身とされている。
天正4(1576)年の奥書がある『播州故事考(ばんしゅうこじこう)』では、永正10(1513)年のこととして、梛寺にまったく同じ服装をした二人の女性が参詣し、寺僧が不思議と思って見ていると、近くの泉のあたりで一人は消えてしまい、「梛寺の狐」の仕業とされたという。
柱を動かしたり、参詣の女性に化けたり、ここに見える「およし狐」は、一般的な狐の怪異話になっている。おそらくこのほかにも、さまざまな怪異がおよし狐の仕業とされていたのだろう。
また江戸時代以来、およし狐は、紀行文「姫山の地主神」で紹介した姫路城天守閣のおさかべ姫と結びつけられることもあった。寛延3(1750)年の『播州雄徳山八幡宮縁起(ばんしゅうゆうとくさんはちまんぐうえんぎ)』では、「梛寺のおよし狐は女に化けて活動したことが諸書に見える」とし、「ここからおさかべ姫と混同されるようになったのであろう」と述べている。江戸時代の知識人の間でも、両者は本来別物で、後から結びついたものと見られていた。
およし狐がいた梛本には、中世までは梛寺とともに播磨総社(はりまそうしゃ)もあった。梛本の場所は、近世の諸書では一致して、城下町の久長門(きゅうちょうもん)の内側にある岐阜町(ぎふまち)あたりとされている。現在の場所にあてはめると、国立病院機構姫路医療センターや県立姫路東高校の付近になる。当館のすぐ東側である。
さて、およし狐のほかにも、姫路周辺には狐話が多数あった。『播磨府中めぐり』では、「宿村の小六」の話があり、天正3(1575)年の『近村めぐり一歩記』では蒲田(かまた)の「井内源二郎」、才(さい)の「竹次郎」のほか、「福吉狐」、「山本村の鼠狐」、「朝日山大法主の狐」、「又鶴の半まだら狐」、「利生のおしも狐」、「神村の太郎太夫狐」、「管長狐」、「黒岡山のはら斑狐」など多数の狐の名前があげられている。また、天正元(1573)年の成立と伝える『播陽うつつ物語』では、名古山(なごやま)の「万太郎狐」、「黒天狗」、「翠髪」、「釣狐」に化かされた話がある。
こうした狐話の多さは、姫路に限ったことではない。中世末期から江戸時代にかけて、狐の話は全国各地で数多く語られるようになっていた。量的に見れば、狐は江戸時代の妖怪の主役級である。
用語解説
県域の狐話

そのほかの県域でも、狐話は無数と言ってよいほどあるので、いくつか紹介しておこう。但馬の養父市(やぶし)、旧山陰道(きゅうさんいんどう)が通る八木川(やぎがわ)のほとりに、八木と三宅(みやけ)という地区がある。両地区の境には、かつて「琴引きの松右衛門(まつえもん)」や「みみんどうの小女郎(こじょろう)」という狐が出るという話があった。
あるとき、日暮れ時に八鹿から帰ろうとこのあたりを通りかかった別のおじいさんが化かされ、いつまでたっても八木と和土(わつち、三宅の少し西側)の間を行ったり来たりさせられ、気がついたら夜が明けていたという話がある。また、あるときは畑仕事をしているうちに日が暮れてしまって帰ろうとしたおじいさんが、村中の家に火がついているまぼろしを見たともいう。
つぎに丹波篠山(たんばささやま)の狐話。丹波篠山市泉(いずみ)の八幡神社には、明治の神仏分離まで竜泉寺(りゅうせんじ)という寺院もあった。この裏山には、尾の先が白い狐が住んでいたというが、とくに悪いこともしないので村では折にふれてお供えなどをしておまつりしていた。
あるとき、この竜泉寺が火事で焼けてしまい、再建をどうしようかと村の人々は悩んでいた。ちょうどそのとき、少し離れた小枕村(こまくらむら)ではお寺を建て替え、古い材木の置き場に困っていた。そこへ泉村の人が訪ねてきて、代銀を払って後日引き取りにくると約束して帰った。ところが、一月経っても誰も引き取りにこないので、小枕村から泉村に催促に行くと、誰も心当たりがない話だった。しかし、代銀は払ってあるので泉村総出で引き取りにいき、無事竜泉寺の再建ができた。村では裏山に住む狐の恩返しだろうと語り伝えてきたという。
この話はいい話だが、やはり人を化かす話も伝わっている。篠山盆地の南、後川(しつかわ)という谷を経由して摂津国能勢郡(せっつのくにのせぐん=現在の大阪府能勢町)へ抜ける道に、古坂峠(ふるさかとうげ)がある。
あるとき後川の人が篠山の祭りからの帰り道、おみやげのご馳走を二人で担いで家路を急いでいると、一方の男の妻が向こうからやってきて、代わりにご馳走を持ってあげようと言う。これはあやしいと思った男は持っていた小刀で女の胸を刺して追い払った。家に帰ってみると果たして妻は無事だったが、ちょうど夫に胸を刺された夢を見て目が覚めたところだったと話した。夜が明けて峠の現場へ行ってみると、大きな狐が胸を刺されて死んでいた、という話である。
ここまでに紹介した話は、現代の民話集に載せられている話で、人を化かすが命まではとらないものが多い。しかし、江戸時代の書物に出てくる狐にはもっと恐ろしいものがいる。紀行文「近世西播磨の怪談」でも紹介している『西播怪談実記(せいばんかいだんじっき)』に見える、宍粟郡山崎(しそうぐんやまさき=現在の宍粟市山崎町)の話を紹介しておこう。
山崎の市街地から見て揖保川(いぼがわ)の対岸、出石(いだいし)というところには、江戸時代、周辺の幕府直轄領を治める山方役所(やまがたやくしょ)があった。出石の川原は、瀬戸内海へと通じる揖保川水運の起点ともなっていた。
正徳年間(1711~16)のこと、出石の米蔵で狐が子を生んだが、近くの子供が一匹取りあげて遊んでいるうちに死んでしまった。4、5日後、その子供と母親が出かけて帰ってこないので捜索すると、子供は揖保川に沈んでいて、母親は少し離れた比地村(ひじむら)の七里が岡で、葛に巻きつかれ、大きな松の枝につるされて死んでいた。
話を聞いた山方役所の責任者は怒り、領内の狐狩りを命じた。その夜、役所の蔵奉行は、庭にやってきた2匹の狐に、「おまえたちはどこかへ立ち去るように」と諭したので、狐は1匹も捕らえられなかったという。
この話では、子供のかたきを討つために、実際に人の命を奪ったことになっている。どの伝説でも似た傾向があるが、狐も江戸時代の話では、人間にとって恐ろしい存在として描かれる場合が多い。