
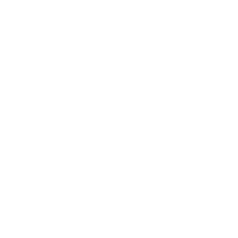 赤松氏の歴史
赤松氏の歴史
守護代所
石見守護代所
揖保郡太子町岩見構
応永5年(1398)から応永29年4月まで、守護代赤松下野入道・肥前守の拠点としてみえ、赤穂郡矢野荘にはそこからさまざまな賦課があり、年始礼もおこなわれていた。
守護家との系譜関係ははっきりしないが、応仁の乱勃発時に播磨を回復した赤松下野守政秀はその後裔と考えられている。
また雪村友梅法嗣を開山とする連城寺・龍源寺といった禅宗寺院も建立され、守護屋形・法雲寺・宝林寺などから構成される赤松地区のような拠点が形成されていた。
この石見について、たつの市御津町岩見に比定されてきたが、国衙領石見郷のほうがふさわしいと考えられる。
寺院は遺称とおもわれる地名が残るのみだが、太子町岩見構には土塁の痕跡が現存し、守護代所にかかわるものだった可能性が高い。

広瀬守護代所
宍粟市山崎町中広瀬あたり
播磨守護代としての宇野氏は早くからみられるが、広瀬と明記されるのは嘉慶2年(1388)が初見。
宇野祐頼・宇野四郎と継承され、応安4年(1397)を最後に、石見の赤松下野入道にかわる。
応安29年に再び広瀬が登場し、宇野越前守・宇野満貴にうけつがれ、嘉吉の乱を迎える。嘉吉の乱とは、嘉吉元年(1441年)に赤松満祐が室町幕府6代将軍・足利義教を殺害したことにはじまり、満祐等が幕府の討伐軍に敗れて討たれるまでの一連の騒乱のことを指す。
広瀬は豊臣期に山崎と呼称されるまでの広域地名で、山崎八幡神社が宇野館(守護代所)とされるが詳細は不明。



