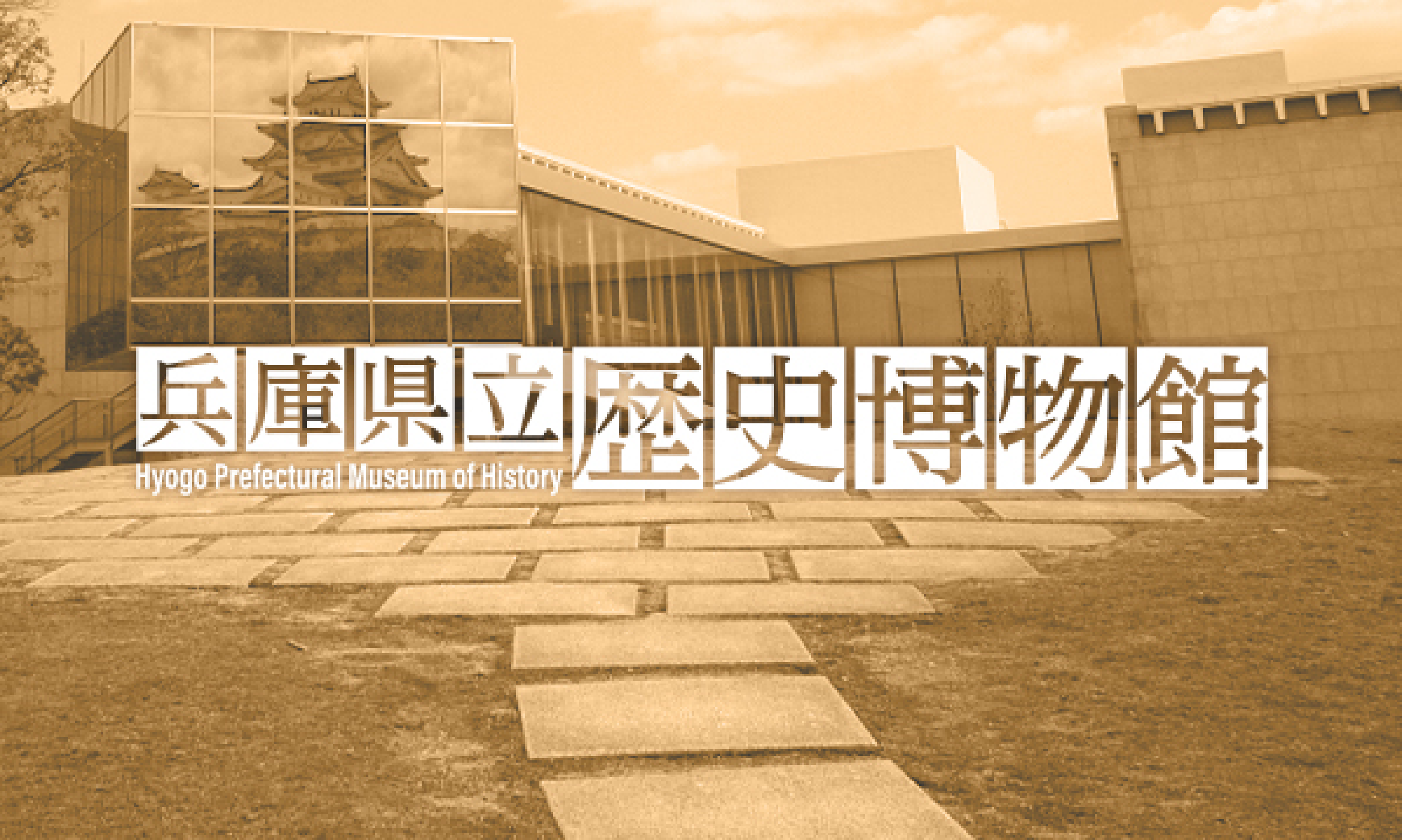学芸員コラム
2016年12月15日
第81回:磁器誕生四百年の旅

昨年の冬に特別企画展「出石焼(いずしやき)-但馬のくらしとやきもの-」を担当させていただいて以来、改めて磁器の魅力に感じ入ってしまった私は、「磁器誕生・有田焼創業400年事業」が行われている佐賀県有田町へと旅に出ました。
磁器は表面の釉薬(ゆうやく)だけではなく素地(きじ)までもが焼成中にガラス化してしまうためか、一見、硬質で冷ややかささえ感じられるような気がします。しかし釉薬や呉須(ごす)による多様な文様や、特に近代出石焼にも見られる多様な造形表現などに、画工や陶工の巧みな技の痕を見出すことができ、単なる美しさを超えて職人の息遣いさえ感じることが出来るような気がしてならないのです。
上の写真は有田の町を散策中に撮ったものですが、店先の看板やランプの笠までもが磁器で出来ているのです。ランプ笠中央の電球を通す穴の周囲4か所に「千客万来」の文字を、それぞれ円を描いた内側に記しています。これらの文字は単に筆書きしたものではありません。まず文字の周囲の輪郭を細筆などで描き、次にその内部を呉須で塗りつぶすという、所謂「濃み染め(だみぞめ)」の技法で描かれています。これらの文字の間を、いわゆる蛸唐草文を手早く描いて埋めており、ランプという日用品でありながらその丁寧な仕事ぶりに感銘を受けた次第です。

上の写真は有田町東部の「泉山」という磁器原料の採掘場です。今からちょうど四百年前の元和二年(1616)、李三平という陶工がこの泉山で磁器原料の産出地を発見し、有田町内の天狗谷(てんぐだに)という場所に窯(かま)を開いたことが、わが国の磁器生産の幕開けとなったということが通説になっています。李三平はもともと朝鮮半島出身の陶工で、文禄慶長の役の後わが国に連れ帰られたと伝えられています。
もっとも最近の調査研究の成果により泉山の発見以前にも、天狗谷窯(てんぐだによう)よりさらに古い窯で磁器が生産されていたことが明らかになっています。しかし泉山で産出された陶石は、近年まで有田を中心とした肥前国の磁器生産を支えてきました。泉山での原料の安定した供給があったからこそ、有田を中心とする広い範囲で磁器生産が続けられてきたといえるでしょう。なお、現在の有田焼は原料を泉山ではなく熊本県天草から調達しているそうです。

李三平が開いたと伝えられる天狗谷窯は現在、国史跡に指定され、その跡地は上の写真のように整備されています。天狗谷には近接していくつかの窯が築かれましたが、当初に築かれた窯は全長53m、焼成室16室からなる長大な窯でした。この窯で焼かれた製品は、同時期の他の窯と比較して皿の割合が少なく、碗や瓶、壺が主体となっている点が特徴です。
有田周辺で磁器を焼き始めた17世紀初頭には、ひとつの同じ窯の中で陶器と磁器を一緒に焼くことが多かったのですが、1630年代以降には専ら磁器だけを焼くように変化していきます。天狗谷窯は実際には磁器創始期の窯ではなく、磁器のみを専ら焼き始めた時の窯と位置づけられており、いわば本格的な磁器生産の幕開けとなった窯といえるかもしれません。
このように有田およびその周辺で始められた磁器の生産は、18世紀後半になると日本各地にその技術が広まっていき、愛知県瀬戸のように広い範囲に製品を流通させる産地も現れるようになります。兵庫県では豊岡市の出石をはじめ、姫路や三田、篠山などで磁器の生産が行われています。

特に出石焼は県内の他の窯に先駆けて、寛政元年(1789)頃に磁器の焼成が始まったと伝えられています。磁器焼成の指導者として、有田の西側、旧平戸藩領の三河内・木原村から兵左衛門という職人が来訪し、出石に磁器生産の技術を伝えたという記述が、出石で陶磁器生産を開始した商人・伊豆屋の日記に記されています。こうして寛政年間に始められた出石の磁器は、当初は専ら藩が経営する窯で焼かれましたが、後に複数の民窯で生産されるようになり、明治期に入ると日用品とともに、海外への販売を視野に入れ、造形に意匠を凝らした白磁が生産されたことで、全国的に知名度が高まりました。現在でも出石焼と聞いて多くの方が白磁を思い浮かべることと思われます。
今回の旅で私は旧平戸藩領まで足を伸ばしませんでしたが、日本各地に伝わる磁器生産の原点に、少しでも触れることができたのではないかと思っています。
【参考文献】
- 大橋康二『有田町史・古窯編』有田町史編纂委員会 1988年3月31日
- 『有田町歴史民俗資料館東館・有田焼参考館展示ガイドブック』2013年3月29日
- 太田陸郎「但馬出石焼窯元古文書(二)」『兵庫史談』11月号 1936年11月10日