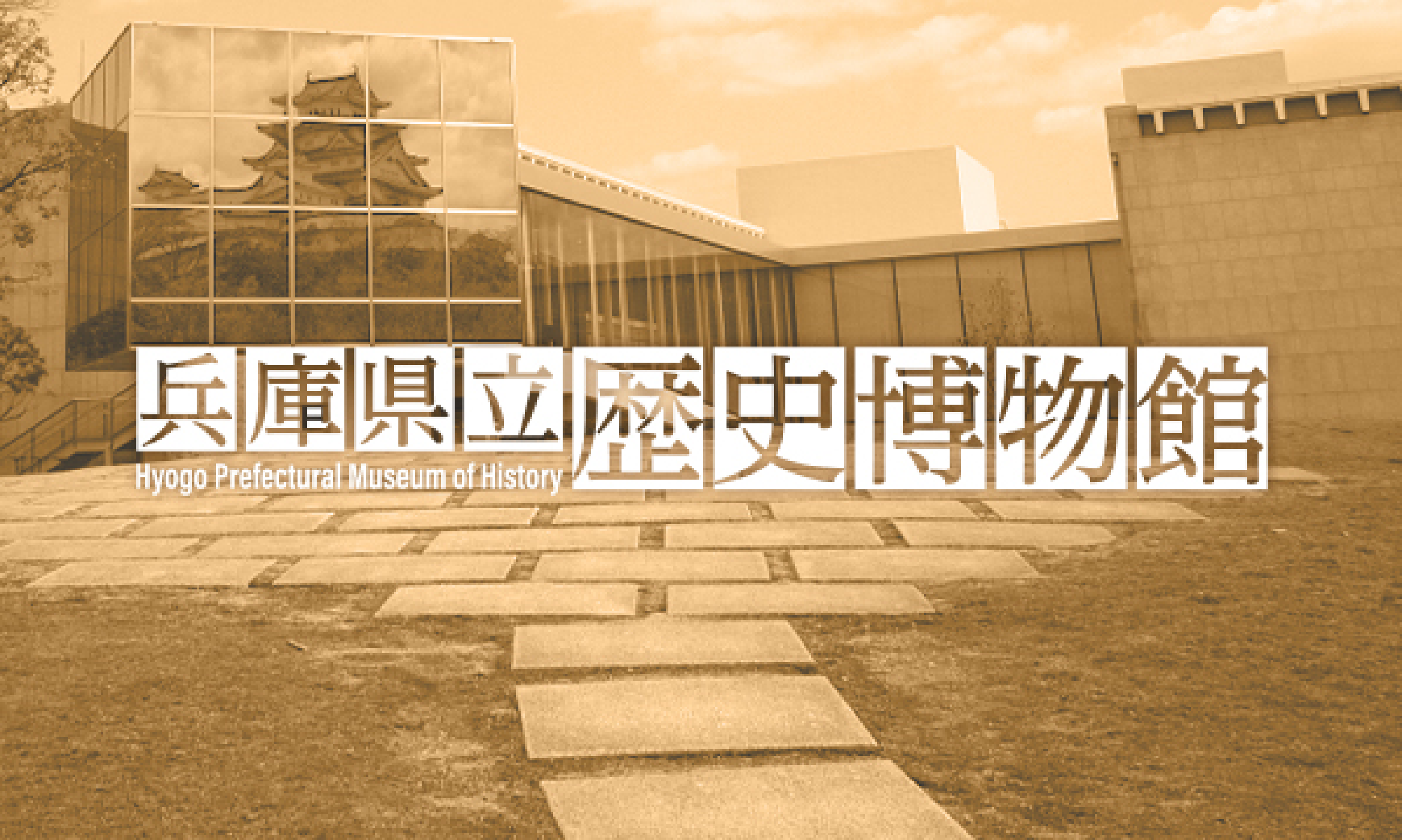学芸員コラム
2014年11月15日
第56回:但馬・出石焼のはじまりの頃
但馬の小京都と呼ばれる出石(いずし)は、江戸時代には仙石氏の城下町として栄えました。近年は名物の出石そばが人気を集め、また明治期の芝居小屋である永楽館が復元されるなど、歴史的なまちなみの保存整備が進められたこともあり、兵庫県内外からより多くの観光客が訪れています。

江戸時代後期、当館蔵(山口コレクション)
出石を代表する伝統的な工芸品として但馬ちりめん、杞柳製品とならび出石焼が人気を集めています。現代の出石焼は純白の地肌を持ち、繊細な装飾が施された白い磁器「白磁」が広く知られています。出石焼の生産が始まったのは江戸時代後半のことですが、江戸時代を通じて出石焼の主力となったのは白磁ではなく、白い素地に青色の顔料で絵付をした「染付(そめつけ)」であることは、実はあまり知られていません。江戸時代、出石焼の窯元ではお椀や皿、鉢、徳利やそば猪口など、染付の日常生活用品を主力として生産し、それらは出石のみならず、兵庫県北部の但馬地域を中心に、人々の日常のくらしを中心に用いられてきました。
ところが、生産が始まったばかりの出石焼の窯で実際に焼かれていたのは、実は「白磁」でも「染付」でもなく、実は丹波の職人によって伝えられた「陶器」であったというのは、さらに知る人の少ない事実ではないでしょうか。

実際のところ、陶器と磁器の区別を説明することは容易ではありません。伊豆屋弥左衛門の日記の中で、陶器は「土焼き」、磁器は「石焼き」と記されています。その表記のとおり陶器は粘土を材料とし、1000℃~1300℃の高温で焼きます。表面の釉薬は溶けてガラス状になりますが、素地はガラス化することはなく多孔質の状態を保ちます。これに対し「石焼き」と記された磁器は、陶石に粘土を混ぜたものを材料とし、1300℃以上の高温で焼いた結果、材料の中の鉱物も溶け、釉薬および素地ともにガラス化したものなのです。素地までガラス化している磁器の場合、割れた破片で手を切る危険性も高いように思われます。
最初の出石焼は天明4年(1784)、出石の商人である伊豆屋弥左衛門によって陶器の生産が始められました。伊豆屋弥左衛門の日記によれば、焼き物の著名な産地である丹波から久八という職人を雇い、さらに京や大坂からも陶工を雇い入れ、松割木の払下げや資金貸与など出石藩の援助を受けて、出石城下町よりおよそ1.5キロメートル西に位置する桜尾という場所に窯を築き、陶器(土焼き)の生産を始めたのです。
桜尾の陶器窯では茶碗などの日常生活用品とともに、出石藩主に贈答するような花生けなども焼かれていたことが、伊豆屋弥左衛門の日記の中に記されています。ところが、操業開始して間もない天明8年(1788)に桜尾窯で火災が発生し、作業場や窯の覆いを焼失するなどの被害を受けました。火災とともに販売不振に陥るなど、出石焼創窯は苦難に満ちた船出であったことが伊豆屋弥左衛門の日記から窺われます。近年、出石焼草創期の窯跡である桜尾窯の発掘調査が豊岡市教育委員会により実施され、土もの(陶器)を焼いていた創業当初の生産の様子があきらかになってきました。いままで文献資料のみでしか知られていなかった出石焼誕生当時の生産の実態が、出土品を中心とした今後の調査・分析を通じて明らかになることが期待されます。

伊豆屋の陶器窯経営が不振に陥っていた寛政元年(1789)と寛政5年(1793)の二度にわたり、肥前国平戸領の石焼き(磁器)職人である兵左右衛門が出石に来訪し、二度目の来訪時に磁器の試作に成功しています。肥前国とは江戸時代初頭にわが国で最初に磁器生産が始められた場所です。江戸時代初頭に生産が始まった肥前国の磁器は、その積み出し港の名にちなんで「伊万里(いまり)」と呼ばれてきました。江戸時代の伊万里の職人は他藩領へ出て行くことが禁じられていましたが、18世紀末から幕末にかけて各地に磁器が生産されるようになりました。そのような背景のもと、出石でも18世紀末に伊万里の磁器職人から技術を学び、寛政年間に磁器焼成を成し遂げました。それが繊細な白磁に代表される現代の出石焼の礎となったのです。