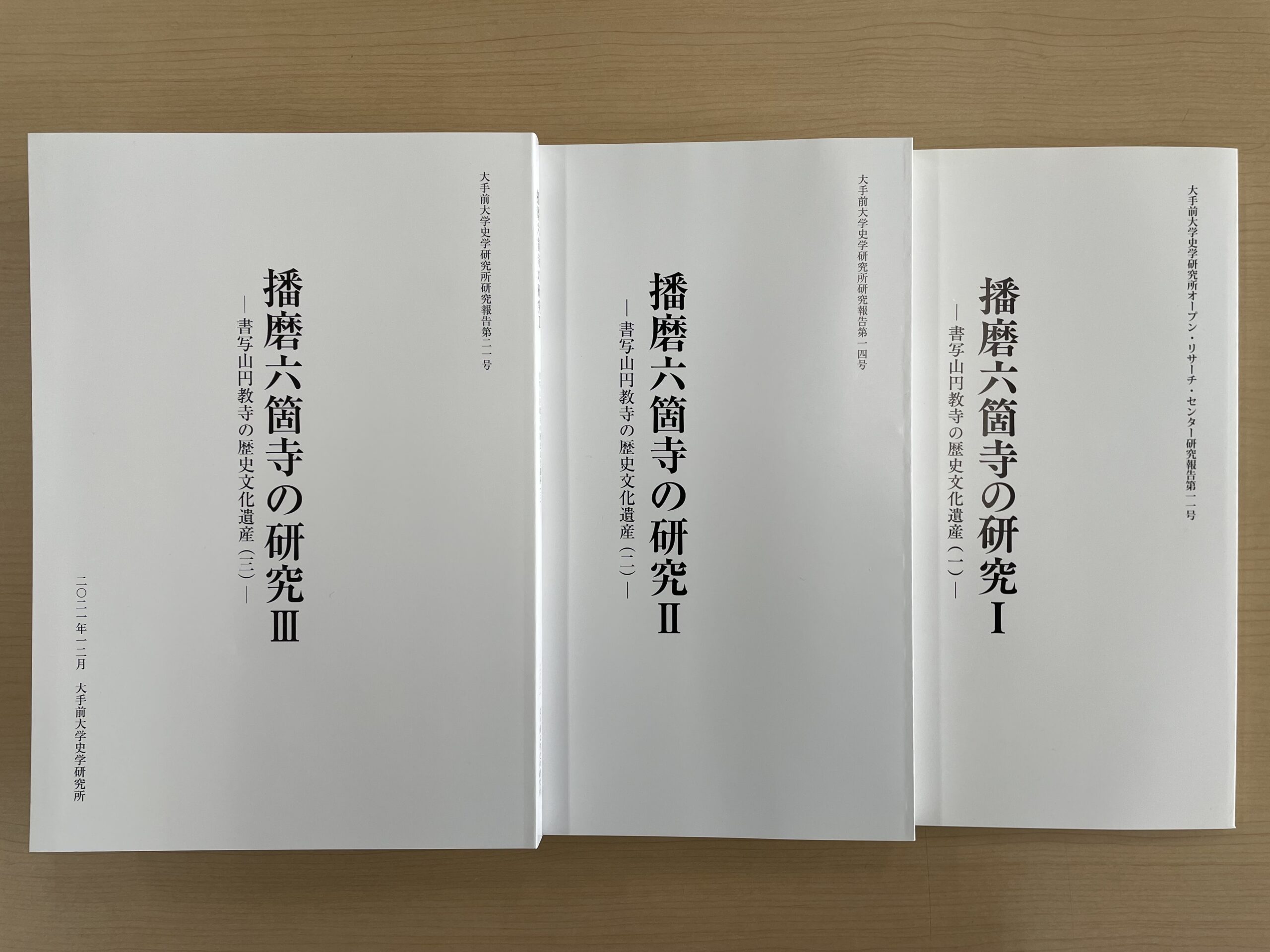研究員のブログ
2020年9月8日
研究員のリレートーク
研究員のリレートーク 第9回 -たたら製鉄研究班から-「鉄は社会を映し出す」
ひょうご歴史研究室研究員 土佐 雅彦
曖昧な記憶で申し訳ないが、1980年代初め、新日鉄社長が「鉄がダイコンに負けた」と社内報か何かでお話されていた。当時、高炉銑(生産されたばかりの鉄)のトン当たり価格が5万円程度(キロ当たりでは約50円)となり、同重量のダイコン価格にとてもかなわないといった趣旨だった。一方で、日本の粗鋼生産量は年間1億トンを突破し(ピーク自体は1973年)、国民一人当たり1トンもの鉄を産み出した国家は歴史上存在しないとも言われた。ちょうど『ジャパン・アズ・ナンバーワン』がよく読まれていた頃で、日本の繁栄を根底から支える製鉄業の役割を象徴しているように感じた。
現在は、中国が世界生産量16億トンのほぼ半分を占めており(『大地の子』が描いた日中両国製鉄マンらによる感動的な技術移転の話も思い出される)、日本の製鉄会社もよく健闘しているとはいえ、国内各地で高炉の休止があいつぎ、新型コロナの影響によりさらなる生産の縮小が懸念されている。鉄を生産する最新の技術や能力は十分にありながら、経済的合理性(採算が見合うか)から国際競争で苦戦を強いられている姿は、鉄の歴史を学ぶ者としてつらいものがある。
歴史的にみて、鉄の生産はそもそも経済的合理性にかなうものであったのだろうか。鉄製品を使用し始める弥生時代から古墳時代前半では、製品や鉄の素材を朝鮮半島南部からの移入に頼っていたと一般に考えられている。交換する物品などの価値にもよろうが、その場合、相手の言い値にならざるを得ないだろう。鉄の生産が始まる古墳時代後半から古代にあっては、鉄の需要が先にあり、経済的合理性以前の問題として懸命に生産の増大が模索されていく。それまで西日本に限られていた製鉄遺跡(長方形箱型炉)が白鳳時代には東日本の各地に出現し、福島県で爆発的な増加をみる。奈良時代に入ると東日本の製鉄炉が半地下式竪型炉へと置換し始め、平安時代には広く普及して九州にも伝播していく。そのありようは、西日本を基盤に成立した律令国家が、東日本を中心とした周縁部を巻き込んで急速に体制を拡大整備し、やがて王朝国家体制へと変質した後も経済的に発展していく過程を如実にあらわしているといえよう。中世では不明な点も多いが、鉄および鉄製品が商品化されていくとともに、経済的合理性が産地間競争をうみ、播磨を含む中国地方を鉄の産地として収斂させ、企業としての近世たたら製鉄へと発展させていくのであろう。その一端は研究室紀要第4号の「たたら製鉄から近代製鉄へ」でふれた。また、9月19日(土)には、シンポジウム「近世播磨のたたら製鉄―その実像を探る―」が開催される。
話は変わるが、日本刀の素材不足に悩む全国の刀匠が、日本美術刀剣保存協会を動かし、日立金属安来製作所の協力を得て、1977年から「日刀保たたら」を復活させている。私も「玉鋼」が欲しくなって購入したら、260グラムで8千円余りであった。やはり特別な需要では、経済的合理性にさほど意味はないことが分かる。それにしても、和鉄の魅力は尽きない。「玉鋼」の輝きをご覧ください。