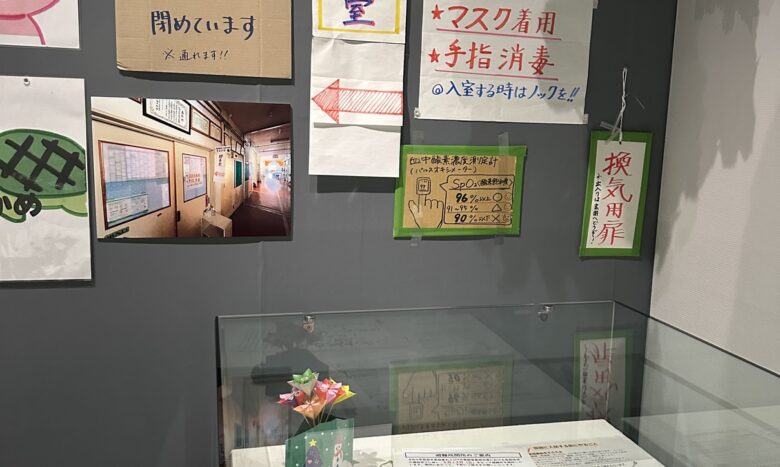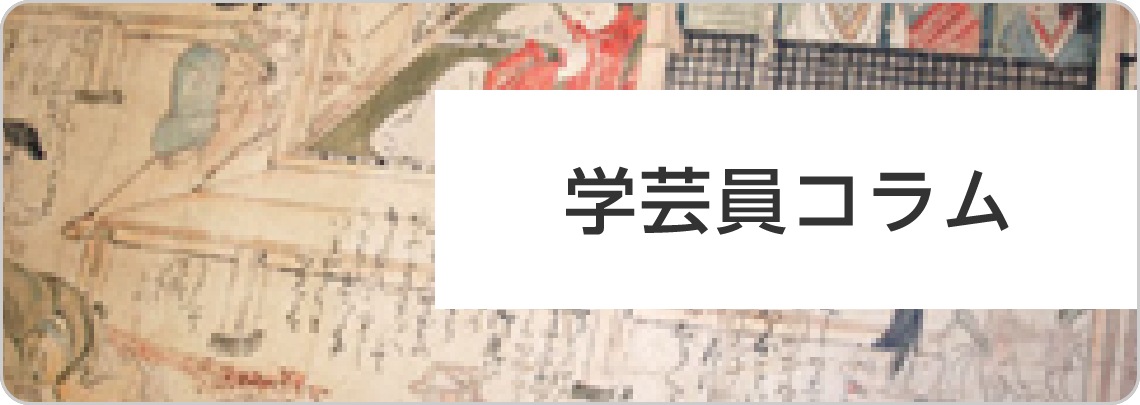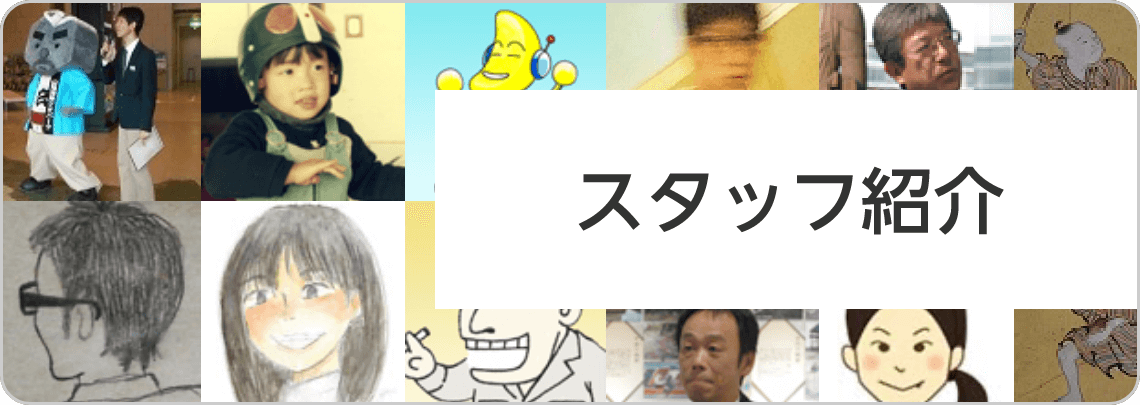館長ブログ
2025年8月1日
新館長によるブログが始まりました!
前任の藪田貫館長を引き継ぎ、2025年4月に第5代館長に就任いたしました奥村弘です。私は、神戸大学文学部での卒業論文で、幕末維新期の地域社会の変容や地方自治形成をテーマに、赤穂や姫路をフィールドとして研究を開始しました。以来、現在にいたるまで、江戸時代から明治大正期に至る地域社会の形成と展開について、県内を中心に研究を進めています。史料の閲覧や研究のヒントをいただくなど、県内の歴史関係者や市民の方々のご支援のもとで研究を進めることができ、とても感謝しております。
研究成果は、神戸市、姫路市、赤穂市、相生市、小野市、三田市、猪名川町などの自治体史の執筆にも反映させて参りました。兵庫県は日本の縮図といわれるとおり、人々のなりわいも多様で、それぞれのところで、ユニークな地域運営が行われてきました。またその多様性を前提とした近代初頭の兵庫県での地方自治形成の在り方は、日本各地で通用する全国のモデルとされるような位置にあり、日本近世・近代史を考える上でも重要な意味を持っています。
神戸大学の教員として経験した阪神・淡路大震災は、私の地域の歴史文化との関わり合いを大きく変えるものでした。大震災後、被災した歴史資料の保存と復興への活用、大震災の資料保存と震災の記憶継承を課題とする、歴史資料ネットワークという地域の歴史資料保全にあたるボランティアを歴史文化関係者の方々と立ち上げました。その後、日本各地の歴史文化関係者とともに地震や水害等の大規模自然災害被災地の歴史資料保全、災害の記憶継承のための支援活動を続けています。現在も能登半島地震での歴史資料の保全活動を進めています。この経験を活かし、神戸大学では人文学研究科地域連携センターを創設し、県内各地の歴史文化の関心を持つ市民の方々と地域の歴史文化を未来に伝えるために多様な事業を進めてきました。
館長として、これまでの経験を活かして、県内各地の歴史文化関係者や地域住民の方々と連携して、地域社会が持つ豊かな歴史を探求するとともに、それを未来に伝えていきたいと考えています。またそのために当館の調査・研究・展示・歴史資料の保存活用機能をいっそう充実させたいと考えております。ご支援のほどよろしくお願いいたします。
さて、兵庫県立歴史博物館では、7月12日から8月31日まで特別展「描かれたお城と城下町」を開催しています。近世のお城は、その軍事的機能等を中心に単独でとらえられることも多いのですが、私のような近代地域史研究者から見ると、どうしても「お城と城下町」が一体化されている絵図に関心が行きます。1871(明治4)年の廃藩置県以降、藩主は東京在住が基本とされるなかで、領主支配によって支えられていた城下町は存続の危機に陥ることになり、それが日本の近代都市形成の起点において重要な問題になっていきます。そこから、城郭と城下町がワンセットという一見あたりまえのことが、近世社会の成り立ちの根幹にあることがうかがえるからです。
今回の特別展では、ポスターの図柄にもなっている「姫路城図屏風」をほぼ30年ぶりに展示しています。この屏風では、姫路城だけでなく、西国街道沿いとみられる城下町の中心部の町屋が詳細に描かれています。建築史・都市史の専門家である大場修さんは「姫路城下の町屋と町並み」(播磨学研究所編『城下町姫路と播磨』神戸新聞総合出版センター、2024年)で、この屏風を紹介し「今は失われた城下の町並みを詳細に描き、その資料的価値は高い」と述べられていますが、私も屏風を見ながら確かにその通りだと感じました。なお播磨学研究所の特別講座「姫路の城下と播磨」を基礎とした同書では、姫路の城下町について多様な論点が提示されています。ぜひご味読いただければと存じます。