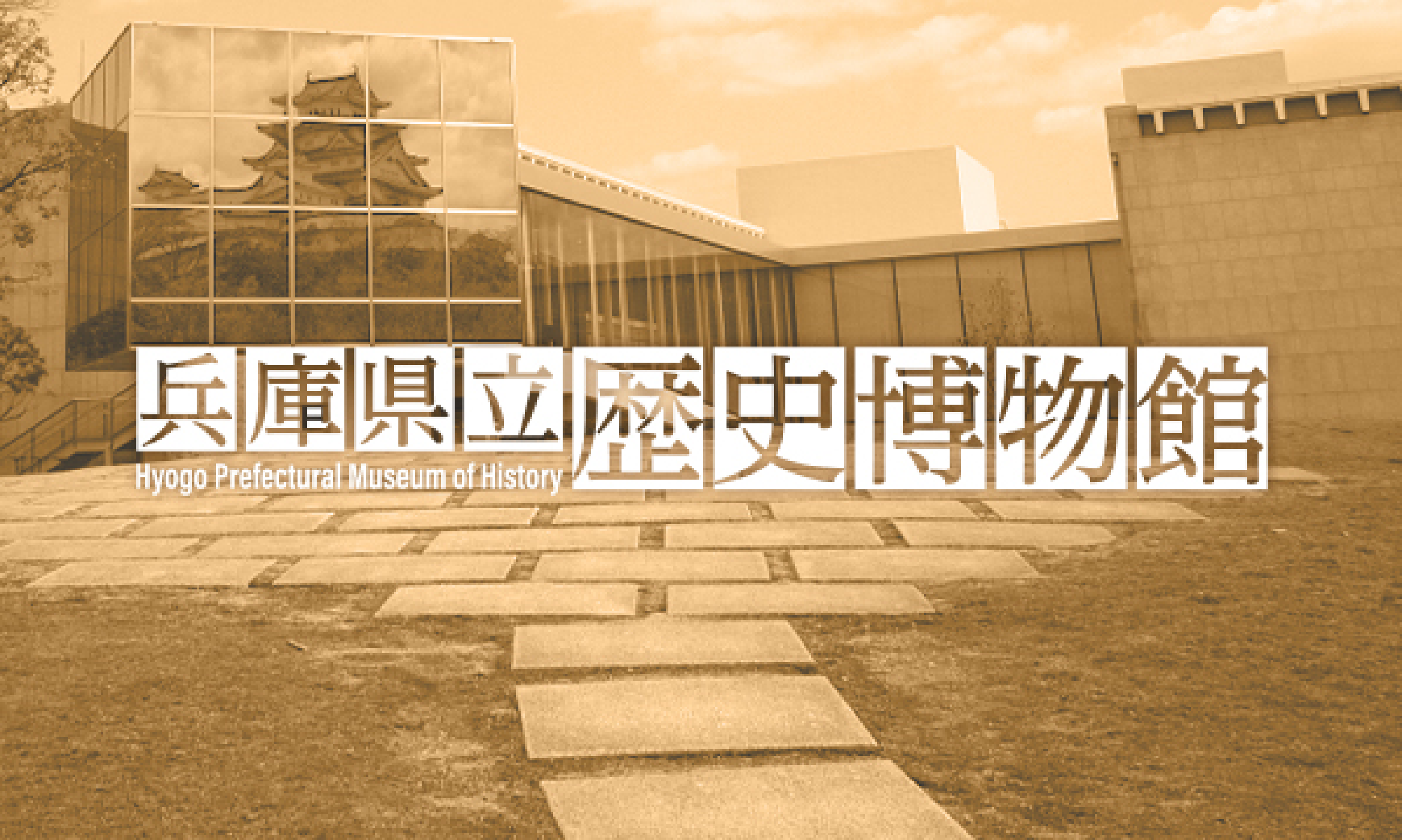学芸員コラム
2015年4月15日
第61回:川/河-「天上のまやちゃん」補遺-
「ひょうご歴史ステーション」では、まもなく平成26年度の新コンテンツとして「デジタル展覧会」を設置し、そのなかの最初の番組として「天上のまやちゃん」をアップしました。(※このコラムの内容は、「天上のまやちゃん」のエンディングにもふれていますので、ぜひコンテンツをお楽しみの上でお読みください。)
この「天上のまやちゃん」では、ブッダのお母さんがブッダに会うために、ある日、天上から下界に降りてきます。ところが途中で、雲から落ちて記憶喪失になってしまい、人間界や動物の世界、阿修羅(あしゅら)たちの世界、餓鬼(がき)たちの世界、はたまた地獄(じごく)……といった六道(ろくどう)の世界を巡(めぐ)ります。ここでは「川/河」がくりかえし登場し、行く先を示すモチーフとして重要な役割を果たします。
そこで今回のコラムは、この「川/河」について、すこしだけ説明をつけたしたいと思います。

全8章のストーリーのうち「川」が登場するのは、第4章・第5章・第6章・第7章・第8章の5章分です。このうち第6章は、章名のまま「賽(さい)の河原(かわら)」を舞台としています。
賽の河原とは、子どもが死後に行くという世界。中世の日本で考案されました。
賽の河原を英語に翻訳すると、”the Children’s Limbo(子どもたちの煉獄《れんごく》)”や”the banks of the Sanzu River(三途《さんず》の川の岸)”となるようです。「子どもたちの煉獄」はともかくとして、はたして賽の河原が、「三途の川の岸」に位置する世界であるのか? 三途の川に賽の河原がある、という説をわたし自身はこれまで聞いたことなかったのです。(もしご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。)
賽の河原と呼ばれる実在の地名は、わたしの知る限り、けっこう身近にあります。法華山一乗寺の奥の院や、宮島の弥山、加賀の潜戸など……、ときどきうっかりと足を踏み入れてしまうほど、身近です。かつては箱根の芦ノ湖にもあった、という記録もあります。ご当地「賽の河原」は、子を亡くした母の思い、父の思いに応えるため、さまざまな地域で必要とされていたにちがいありません。
では三途の川って、どこにあるのでしょう?
手がかりの一つが、地獄を記したお経です。
中国撰述の偽経(ぎきょう)「十王経(じゅうおうきょう)」には、奈河(なが)という川が、初広王(しょこうおう)の王庁の近くを流れていることが記されています。ちなみに初江王は、閻魔王(えんまおう)の同僚で、十人の王うちでも最初の死者の裁判を担当します。
この川のたもとには、脱衣婆(だつえば)という老婆(ろうば)がいて、この川を渡る死者から着物をはぎとる、ともいいます。
この地獄の手前を流れる奈河、すなわち奈落の川は、三途の川のイメージと重なるようです。
そうだとすれば三途の川は、地中深くにあるという地獄と、死者の裁きを行う冥府とのあいだに位置しており、けっこう近い距離感にあると推測されます。

そして、この三途の川の岸辺に、賽の河原があるのだとすれば、子どもたちも大人たちと同様、死後に冥府や地獄の近くの世界に堕ちていることになります。
それでは賽の河原は、三途の川の渡しとは、どれくらいどの方角に離れているのでしょう?
そもそも三途の川はどこからきて、どこへとそそぐ川なのでしょうか? 小石があるような河原は、川の中流域あたりかと思いますが、よくわかりません。
いまいちすっきりとしません。
考えれば考えるほど、煮つまってしまいそうです。
視点を変えてみましょう。
「此岸(しがん)」と「彼岸(ひがん)」という言葉があります。
煩悩(ぼんのう)を中間の川や海にたとえるところから、生きているこの世を此岸として、悟りの世界を彼岸というようです(『日本国語大辞典』「彼岸」の項)。あるいは、彼岸は、生死の海をこえた悟りの世界ともされています(『仏教語大辞典』「彼岸」の項)。
つまり「此岸」は迷いの世界、「彼岸」は悟りの世界というわけです。
この「此岸」と「彼岸」のあいだに想定された川や海ですが、これは輪廻転生のある迷いの世界の延長でもあり、なおかつ彼岸はもはや人間の世界ではないことから、生と死を分かつ境界のようでもあります。そしてこの川や海には名前がありません。そもそもが比喩なのですから、固有の地名と結びつくはずはないのです。
それにしても、この迷いや煩悩のたとえである川や海の性格は、まるで三途の川のようではないでしょうか。
川の手前に生死や迷いがあり、川の向こうに悟り《涅槃;ニルヴァーナ》の世界が存在する。
三途の川の手前は、此岸である生きた人間の世界。三途の川の向こうは、彼岸である死者たちの世界。
さらには川を渡りきらないと、悟りの世界や地獄(まったくの正反対ですが)には到れない……。
どちらの川も、たしかに場所は茫漠としているのですが、性質が似ています。
大きな川の両岸に、悟りと生死、迷いといった人間の可能性・潜在性がすべて収められているという発想が認められます。
川の両岸に人間の可能性をたとえるという発想は、インドと日本とで共通するものなのかもしれません。あるいは、インドや中国から伝わった思想が、のちの日本でも共有されていたのでしょうか。

悟りについて付け加えれば、お釈迦さま(ゴータマ・シッダールタ)がはじめて悟りをひらいたのも、悟りを完成させたのも川の岸辺でした。
ブッダガヤの尼連禅河(にれんぜんが)という川のほとりで、菩提樹の下にて悟り、ブッダとなったと信じられています。いっぽうで、お釈迦さまが亡くなったのも川の岸辺です。これを涅槃(ねはん)といい、肉体を離れて悟りを完成させたととらえられています。クシナガラの跋提河(ばっだいが)という川のほとりで、沙羅双樹(さらそうじゅ)のあいだに横たわり、お釈迦さまは涅槃に入られました。
このように、川岸という場所は悟りや死という人間の可能性・潜在性と、結びついているようです。
「天上のまやちゃん」の「第7章 来迎(らいごう)」と「第8章 涅槃」でも、それぞれ川が登場します。このストーリーの中で、地獄ちかくの三途の川や、賽の河原、跋提河などを一本に連なる川として描いたのは、悠久の仏教文化において築かれてきた川岸と人間の潜在性の重層的イメージを、織り込みたかったからでした。
きっと昔の日本人も、三途の川や賽の河原、尼連禅河や跋提河といった仏教に登場する川に関して、地理関係をすっきりと理解できないままに、それでもばくぜんと思い描きながら、川岸のイメージを心にそぐうものとして形づくっていったのでしょう。
逆に、地理関係がばくぜんとしているからこそ、さまざまな実在の地を「三途の川」や「賽の河原」として地域でイメージを共有し、ご当地「あの世」を形成することができたのかもしれません。
さてさて、この学芸コラムも開始から6年目となりました。「ひょうご歴史ステーション」は12年目に突入です。これからもさまざまな世代のみなさまに楽しんでいただけるよう、工夫を凝らしてまいりますので、どうぞ末永くお付きあいくださいますようお願い申しあげます。