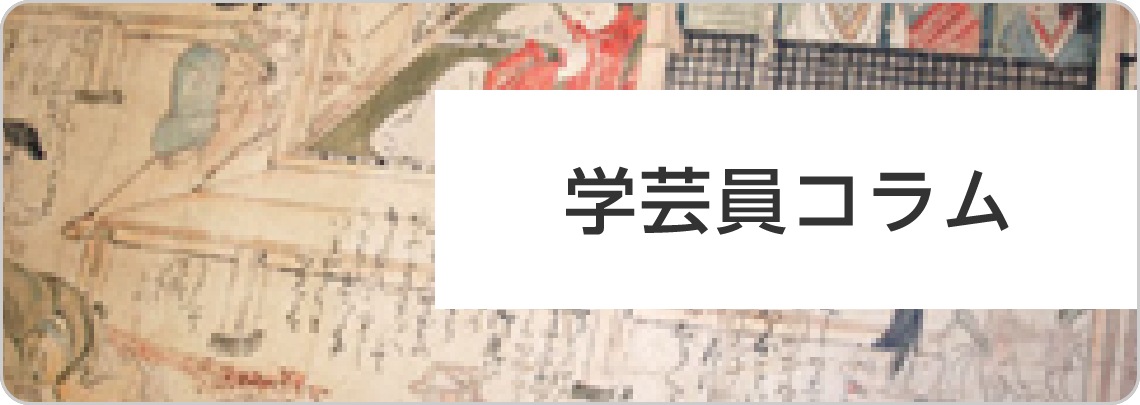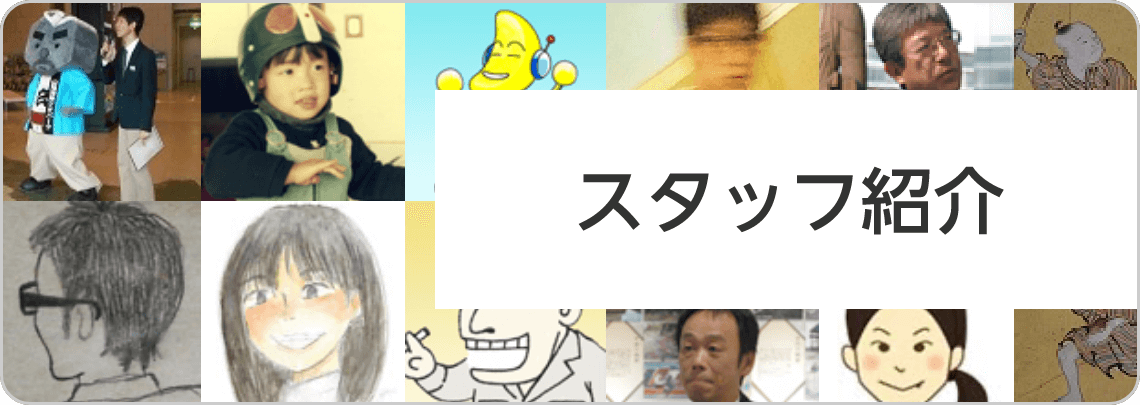わたしは毎日、日記を付けている。五年日記帳を愛用しているが、付け始めは1991年元旦で、三年日記であった。なぜ付け始めたかといえば、それ以前、江戸末期のひとりの女性の日記に出会い、それを解読するなかで、「日記を付けるとはどういうことか」――自分で体験してみよう、という思いたったからであったと記憶する。
しかしそれが、30年を超えて現在まで続くとは予想していなかった。いまやもはや癖で、忘れた日は翌日に書く。基本、万年筆で書くが、海外滞在中は、パソコンに頼ることもあり、その場合、後日、日記帳に張り付けている。したがって30年余の間、空白の日はない。
もちろん1995年1月17日(火)の記事もある。
明け方猛烈な地震で飛び起きる。午前5時46分!終日、余震何度もあり、食欲進まず、眠れず、TVつけっぱなしで阪急運転再開を待つもメド立たず。午後、下山してshopへ。電池売り切れ!!TELするも通じず、公衆電話にて母へTEL。その後、神戸・西宮などの大災害が報じられ、不安募る。
生死の境に立っていなかったから書けたこの記事。読むだけで、TVが映し出す災害映像など、さまざまな記憶が蘇る。
日記によれば、翌18日には、西宮で被災した大学時代の教え子が母娘(当時2歳)でやってきた。余震が続いたからで、二泊して帰って行った。そして20日には大学に出かけ、日常が戻っている。さらに27日には、上京して群馬高崎で催された教え子の結婚式に出ている。まったく忘れていたが、わたしの身辺は震災一色でなかったことを日記は教える。被災地との違いは決定的に大きい。
29日(日)には、被災した友人の住む明石に、小学生の息子二人と見舞いに出かけた。ビニールのバケツと携帯ガスコンロ一式を持って。被災者の必需品であったが、大阪では十分、調達できたのである。
日記には、そのルートが記されている。
行き 大阪天保山―高速船―神戸港―JR神戸=バス=須磨―JR明石
帰り 明石―加古川―粟生―三田―大阪
行きも帰りも5時間の行程。高速船はぎゅうぎゅう詰めであったのは覚えているが、この時、JR加古川線に乗っていたことは忘れていた。記憶ではすでに細部はボヤけているから、書かれた記事は鮮烈。その一方、書いていないが、神戸港からJR神戸まで歩いた道中の景観は覚えている。文字と記憶は、互いに交差することで過去の解像度を上げる。この度の特別展は観覧者にとって、そんな機会となっているのではないだろうか?
もうひとつ、大きな出会いがあった。大震災がもたらした出会いである。それは5月6日(土)、尼崎市総合文化センターで開催された「阪神・淡路大震災 歴史と文化をいかす街づくりシンポジウム」である。8名の報告者の一人として参加したが、当日の日記には、こう記されている。
阪神震災シンポでreport。気のりせずも、関連して聞く報告は大いに有益。コンパのち帰宅。
関連報告の一つが、神戸大学奥村弘氏の「被災史料の状況からみた資料保存の課題―史料ネットの活動から―」。いまでは全国的な組織となっている史料ネットの第一声である。震災30年は、史料ネットの30年でもある。
最後に、30年前の1995年の、わたしにとってもう一つ大きな出来事について――
9月6日(水)、日本を離れ、ヨーロッパの小国ベルギーに向かったのである。ルーヴェン・カトリック大学に遊学する機会を得、帰国は11月6日(月)。この間、日記は、持参したパソコンに舞台を移している。
はじめての長期の海外滞在で、夫婦とも異国の生活を満喫したが、その2か月の間に、わたしは変わった。帰国時、顎髭を蓄えて帰国したのである。その髭姿、いまではそれがフツーで馴染んでいるが、帰国時老母は一言、「なんやそれ、東郷元帥みたいや」と呟いたのである。
母はすでにこの世にいない。が、わたしの髭姿は健在である。